秋分を迎える前に ― 夏の疲れを癒す東洋医学の知恵
まだまだ暑い毎日ですが、秋分の日が近づき、朝晩にはようやく秋を感じることも増えてきました。
本来、秋は気温が少し下がり始め、空気も乾燥してくる時期ですが、ここ数年は厳しい状況が続いています。
今年は特に6月に梅雨らしい梅雨がほとんどなく、暑い期間が長くなっていました。
そのため、夏の疲れが出て、今後は全国・全世代で不調が起こる可能性が高いです。
すでに、コロナやリンゴ病、百日咳といった感染症が長く流行しています。
夏の疲れに加え、運動会(練習を含む)、マラソン大会、秋祭りなど楽しいイベントが、不調のきっかけになることもあります。
では、なぜ今後不調が増えるのでしょうか?
東洋医学ではさまざまな視点で考えられますが、ここでは五臓六腑の働きをもとに解説していきます。
夏は「心(しん)」の季節
夏は火の臓である「心」の季節です。
心は身体のエンジンにあたります。四季の中でも夏は活動のシーズンであり、活発に動くこと、植物でいえば大きく成長する時期にあたります。
心が元気であれば、この夏は活動的に過ごせたはずです。
しかし近年は猛暑・酷暑の影響で、心がオーバーヒートしている可能性が高まっています。
夏は心が主役なので、多少オーバーヒートしても乗り越えられます。
ただし、立秋(8月7日)以降は秋に入り、働き方が変わってきます。ちょうどこの頃から夏の疲れが出始めると考えてください。
例年であれば「夏バテ」や「夏風邪」が現れるのもこの時期です。
冷房の部屋にいた人も例外ではありません。
「酷暑」と「冷房」という寒暖差のダメージは、かえって大きくなることもあります。
心を支える「腎」の働き
夏に心がフル稼働すると、それを支える臓があります。
水の臓である「腎」です。腎は身体を冷ます働きがあり、自動車にたとえるならエンジンが「心」、ラジエーターが「腎」となります。
この暑い夏、腎は必死に身体の熱を冷ます仕事を6月から続けてきました。昨年に続き、今年もかなり負担がかかっています。
そのため、腎が相当疲れている人が多いと考えられます。
腎が弱ることで、心のオーバーヒートを抑えきれず症状が出たり、腎そのものの不調として
・腰痛(ぎっくり腰)
・耳の閉塞感
・耳鳴り
・めまい
といった症状が出やすくなります。
秋から冬にかけて注意したいこと

11月から12月(今年はもっと早いかもしれません)にかけて、ウイルス性の感染症が流行する可能性があります。
東洋医学では、
• 心がオーバーヒートして熱を持つ
• 腎が弱って身体の潤いや冷ます力がなくなる
このように疲れが重なった時に、ウイルス性の問題が発症しやすくなると考えます。
今年もすでにこの状態が出来上がりつつあります。
さらに、急な冷え込み、運動会後の疲れ、ストレスや仕事の疲労などが引き金となり、症状が出てくるのです。
不調を防ぐための養生法
発症を防ぐには、まずは 早寝。
秋分の日以降は昼より夜が長くなります。夜が長いということは、それだけ睡眠が大切になる時期であり、活動時間も減らす必要があります。
次に、腹八分目。
内臓が活発に働くと熱エネルギーが生じます。オーバーヒート気味の今は、少し休ませてあげるくらいがちょうどいいのです。
そして、目の酷使を避けること。
PCやスマホの使用は避けられませんが、視覚の使いすぎは「心」をオーバーヒートさせます。すでに負担がかかっている心に、さらにダメージを与えてしまいます。
まとめ
完全に不調が出ないことが理想ですが、疲れは何らかの形で現れます。 昭和56年1月30日生まれ。奈良県吉野郡下市町出身
「大難を小難に、小難を無難に」。
本格的に季節が移り変わる前に、生活を整えて疲れを取りましょう。
鍼灸は効率よく疲れを取るサポートになります。症状が出る前、少し疲れを感じた段階での施術がおすすめです。ぜひご相談ください。
山本達也
出身校
奈良県立耳成高校・奈良産業大学
東洋医療専門学校・大阪医療技術学園専門学校
保有資格
「はり師・きゅう師」「はり師教員・きゅう師教員」
職歴・活動
岐阜保健短期大学医療専門学校2009~2012まで専任教員として勤務。岐阜保健短期大学にて2年間、非常勤講師を務める。
現在は鍼灸院と並行して、東洋医学の普及、若手鍼灸師育成の為、セミナー・勉強会を実施
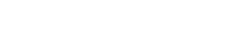


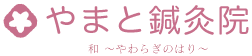


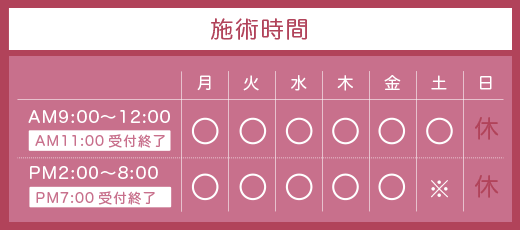

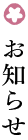
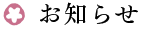
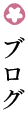
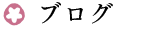
コメント